
2025年度「オンライン園内研修」
2025年度は、以下の(1)〜(12)の講座をお届けします。
園の年間スケジュールに柔軟に対応できるように、
配信期間を年度中
(2025年5月〜2026年3月末)とします。
様々なテーマから選び、
園内の全職員で学びを共有してください。
2025年度の新しい研修ラインナップ
年間のスケジュールに合わせて、様々なテーマから選び、職員全員で学びを共有してください。
(1)子どものことばの獲得と学び 〜ことばの力と思考の力をどう育てるか(講師 今井 むつみ)
(2)保育者の役割をアタッチメント、集団共同型育児、赤ちゃん学の視点から学ぶ~子どもと信頼しあう保育者になるために(講師 遠藤 利彦)
(3)子どもの育ちを阻む「メディア」の影響を学ぶ〜「対人関係」「生活リズム」「遊びと依存」の視点から(講師 原 陽一郎)
(4)子どもの把握と理解 〜子どもを理解したい保育者のために(講師 高山 静子)
(5)保育の手立て(生活・手順・環境における手順と関わり)について理由と意味を学び直す〜すべての子どもに通じる理解と対応(講師 野藤 弘幸)
好評の研修の再配信
受講できなかった研修を、ぜひこの機会に!
(8) 乳児保育 〜一人ひとりを大切に育てるために(講師 吉本 和子)
※2023年度開催の研修映像の再配信
(9) 育児担当制の保育実践 ~始める、進める、深めるための具体的な手立て(講師 井上章久・井上ゆかり)
※2024年度開催の研修映像の再配信
(10) 環境を通した教育を学ぶ 〜子どもとつくる保育と環境(講師 佐々木 晃)
※2022年度開催の研修映像の再配信
(11) 子どもの発達を支える環境構成 ~「遊びの写真」から保育の知恵を学ぶ(講師 細田 直哉)
※2024年度開催の研修映像の再配信
(12) 発達障害のこどもに対する保育の考え方と取り組み(講師 野藤 弘幸)
※2022年度開催の研修映像の再配信
「オンライン園内研修」は「処遇改善等加算Ⅱに係る研修」の対象です
研修実施主体=株式会社郁洋舎
参加費・配信期間・申込方法・視聴方法
1講座 22,000円(税込)
施設単位でお申し込みください。
配信期間:2025年5月〜2026年3月末日
視聴方法
接続機器数、視聴回数、場所に制限はございません。
施設職員、在園児保護者のパソコンやスマホから視聴可能です。
お申し込み・お問い合わせ
運営事務局 support@ennaikenshu.com
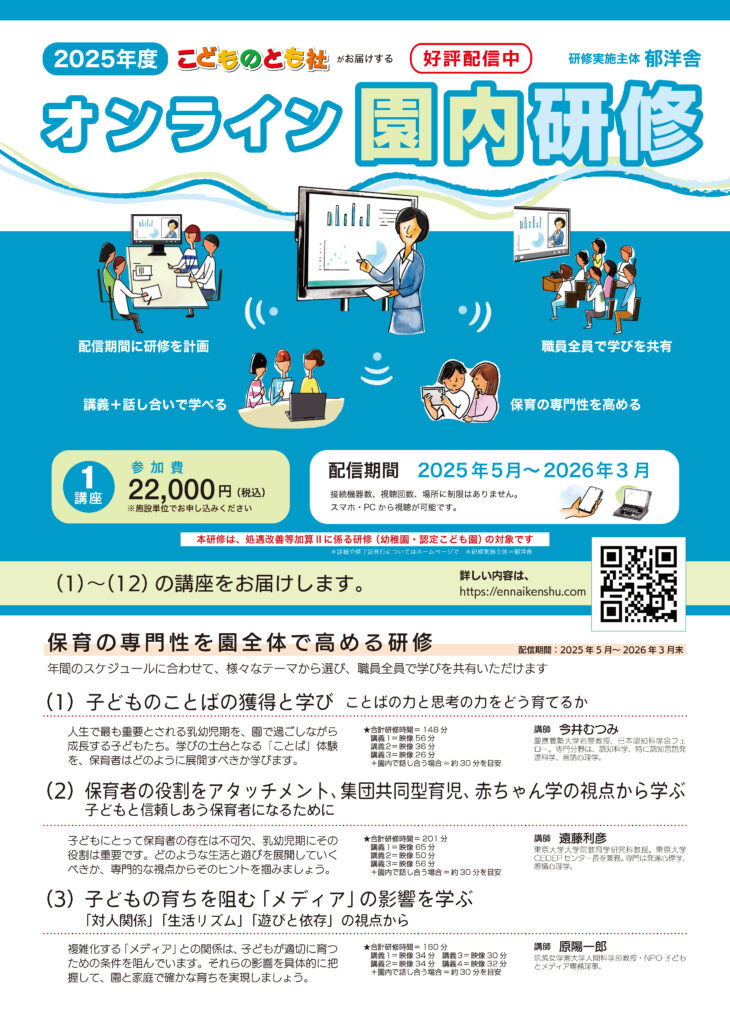
2024年度の研修内容
「オンライン園内研修」が評価される理由
- 園の職員みんなで同じ学びを共有できます。
- 少ない予算と労力で、年間を通した研修を計画できます。
- 講師のスライドなどが見やすく、音も聞きやすいと評判です。
- 普段の場所から、リラックスして参加できます。
- 外部の集合研修への参加を避けて、感染のリスクが低減できます。
